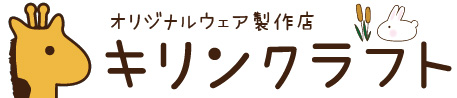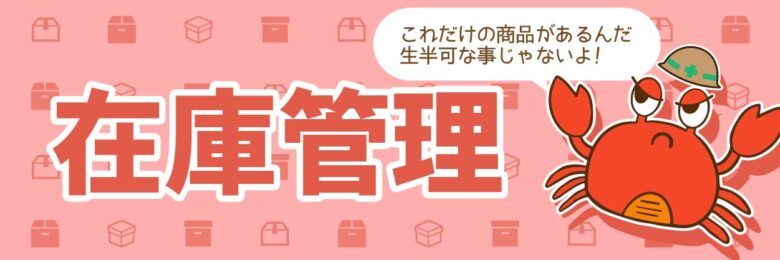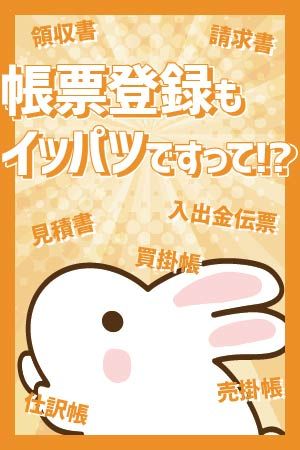「職人の暗黙知」から「形式知のベストプラクティス集積」へ
データベース活用の有無と質によって変わる“経営の難易度”を、直感的なイラストでまとめました。見積ルール(値決め)は会社の戦略、データベース構築は組織の段取りそのものです。
経営難易度の比較
- 属人化:職人の暗黙知に依存しやすい
- ノウハウが散逸、再現性が低い
- 見積のブレ=値決めが戦略にならない
- 先行管理が弱く、シミュレーション不十分
経営難易度:
- ベストプラクティスの集積で再現性UP
- データとマニュアル化=形式知で標準化
- 見積ルール(値決め)=会社の戦略を明確化
- 予測が当たりやすく、先行管理が機能
経営難易度:
未活用は難易度高い
活用で難易度が下がる
ベストプラクティス & 形式知 化
「職人の暗黙知」から「データとマニュアル化(形式知)」へ
暗黙知(経験に基づくコツ・勘)は価値の源泉ですが、そのままでは共有・再現が難しく、属人化を招きます。
ノウハウを形式知としてデータベースとマニュアルに落とし込むことで、共有・教育・品質の再現が可能になります。
データベース構築=組織の段取りそのもの(PDCAに直結)
収集
➡
整理・標準化
➡
見積ルール(値決め)
➡
実行
➡
記録
➡
分析
➡
改善(ベストプラクティス更新)
値決め=会社の戦略。データで裏付け、標準化するほど再現性が高まります。
「未来と過去」を分けて考える:案件管理(PLAN)と会計(CHECK)
案件管理(予測シミュレーター/進捗管理)=未来・PLAN
- 売上・粗利のシミュレーション
- 進捗管理(遅延・リスクの見える化)
- 工数・原価の事前見積と負荷平準化
会計ソフト(結果管理)=過去・CHECK
- 実績:売上/費用/利益の結果記録
- 予実差異の把握、税務・決算
- 結果からベストプラクティス更新へフィードバック
案件管理(未来)と会計(過去)は分けて設計。ただしデータは連携し、PLAN⇄CHECKのループで精度を高めます。
はじめるなら、この最小構成から
- 案件タイプ定義(型)と必要データ項目の洗い出し
- 見積ルール(値決めロジック)の仮説化と係数化
- 進捗ステータス(受注→制作→納品→検収)を標準化
- 予実差を比較できるID設計(案件ID・見積ID・伝票IDの連番)
- ベストプラクティスを蓄積するナレッジDB(検索タグ&更新履歴)
“小さく始めて、更新を前提に回す”ことが成功の近道です。

案件管理システムなら、手間を無くし利益に繋げるFullfree。キリンクラフトの設定代行プランを活用で、ムリなく導入できます。


Fullfreeなら
複数の情報を連携管理!
更新記録も残るから
うっかり上書きも戻ってやり直せる!
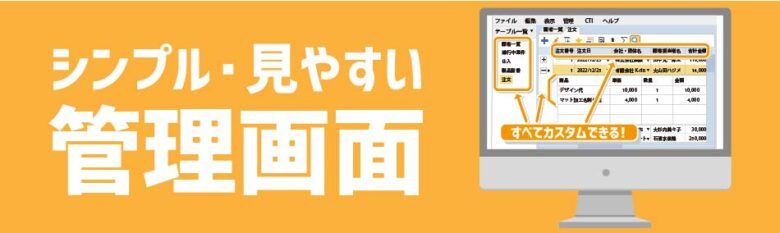
情報の一元化で手間とミスを減らし
利益に繋げるFullfree